我孫子市立図書館で借りた4冊のうちの残り2冊を読んでみた。
いずれも、講談社学術文庫文庫だった。講談社学術文庫は、1976年発足の文庫で、古典新訳や書き下ろしも多く、私もずいぶんお世話になった文庫である。
2000冊以上刊行されているらしいが、著者の肖像が表紙に使われていて、明るい感じになっている。私が、よく読んでいた頃は地味な印象の表紙だった。
スエンソンは、デンマーク海軍の軍人であったが、フランス海軍に出向した。
1866年8月に、フランス海軍の一員として来日した。
翌年5月に、フランス公使ロッシュが将軍徳川慶喜に謁見する際に陪席した。7月に、日本を離れている。
本書の原著である見聞録「日本素描」は、1969年から70年にかけて雑誌「世界各国から」で発表された。
スエンソンだけのことではないが、このような見聞録は自国の人々に読んでもらうために描いたものなので、とても率直に正直に書かれていると思う。
社交辞令は必要ないので、感じたことをそのまま書いているので、かなり辛辣な文章もある。
特に、日本人の容貌や、服装、音楽などに、それを感じる。
彼等の育ったヨーロッパの美的基準が身についているのだから、当然なことである。
一見したところ日本人は、好ましい外観をしているとはとてもいえない。
狭い額、突き出た頬骨、ぺしゃんこの鼻、おかしな位置についてる両の目は、いやな印象を与えかねない。
ところがそれも、栗色に輝く瞳から伝わってくる知性、顔の表情全体からにじみ出てくる善良さと陽気さに接して思わず抱いてしまう共感によって、たちまちのうちに吹き飛ばされてしまうのである。
男たちは一般に背が低い。
下層の労働者階級はがっしりと逞しい体格をしているが、力仕事をして筋肉を発達させることのない上層階級の男はやせていて、往々にして貧弱である。
膚は色白だが、健康で茶色味を帯びており絶えず太陽とふううにさらされている住民の一部では、赤銅色の肌も珍しくない。
日本人の衣服は非常に見すぼらしい。どちらかというと暗い色の無地の生地を好み、服の仕立て、型の優美さにだけお洒落をする。
庶民の服は暖かい季節にはできるだけ軽くされ、腰の部分をおおう帯[褌]一本だけになる。けれども実際はそれすらも象徴的な役割しか果たさず、ほとんど丸裸である。
帰国後デンマーク海軍に帰属していたスエンソンは、海軍大臣の副官となる。
中国と日本へ進出を具体化していた大北電信会社に入社し、ウラジオストックー上海ー長崎間に海底ケーブルを敷設する事業の采配をとるために東洋に派遣された。
見聞録「日本素描」で示されていた、表面的だけでなくもっと深く観察する彼の能力が評価されたのだろう。
著作の中に、次のような文章がある。
ここで日本人の観察をその外見から内面の方に移すにあたって、われわれは最新の注意を払わなければならない。
日本という国を知って間もないわれわれ西洋人は、ほんの短期間の知己を得ただけの日本人一般の性格や特徴について、正しくかつ仔細にわたった描写をするにはいったいどうしたら良いのか。
完全に画一化されている社会を対象としてさえ難しいと思われるのに、日本のようなはなはだ斉一でない要素が混然としている国を相手にした場合、その困難はさらに大きいに違いない。
住民各階級の間に非常に明確な境界が引かれ、その社会的地位がおたがいまったく異なり、その利益も相反するために、国民の性格に種々多様な刻印が押されているのは当然だし、国の一部にとっては真実であることがらも、別の一部では誤りになってしまう。
このような姿勢で日本に滞在していたスエンソンは、いろいろと興味深い観察をして、それを記述している。
日本人は誇り高く自尊心の強い性格で、侮辱に対して敏感、一度受けたらそう簡単には忘れない。その反面、他人から受けた好意には、同じ程度に感謝の念を抱く。
日本人は身分の高い人物の前に出たときでさえめったに物怖じすることのない国民で、私はかつて、まだ年若い青年が、大名やゴロジョー(閣僚会議の一員)[御老中]と、同僚や自分と同じ身分の者と話すのと同じ率直で開けっ広げな会話をする場面に居合わせたことがある。
青少年に地位と年齢を尊ぶことが教えられる一方、自己の尊厳を主張することも教えられているのである。
日本という国は、その構成員がたとえどんなに抑圧されているにしろ、誰であろうと他人にやすやすと屈服するようなことはない。彼らが文句なしに認める唯一のもの、大君から大名、乞食から日雇いに至るまで共通なその唯一のもの、それは法である。
日本の上層階級は下層の人々をたいへん大事に扱う。最下級の召使いが主人に厳しい扱いを受けたなどという例を耳にすることさえ稀である。
主人と召使いの間には通常、友好的で親密な関係が成り立っており、これは西洋自由諸国にあってはまず未知の関係といって良い。
ユーモアがあってふざけ好きなのはすべての社会階層に共通する特徴である。
上流の人間は無理にかぶった真面目くさい仮面の下にそれを隠しているが、威厳を保つ必要なしと判断するや否や、たちまち仮面を外してしまう。
その点、下層の連中は自分の性格に枷をはめるような真似はしない。
大北電信会社で、1873年に部長、874年に常務、1877年に社長に昇進し、1908年までその職にあった。
日本との出会いは、出向先のフランス海軍でたまたま日本遠征に同行したことだと思うが、その後日本との縁は深いものになっていく。
社長になってからは、国際電信に関する不平等な協定の改定を要求する日本政府と再三交渉している。

ハーバート・G・ポンティング 「英国写真家の見た明治日本」 講談社学術文庫
長岡祥三 訳
ポンティングは、イギリスの職業写真家であり、ロバート・スコットの南極探検隊(1910年〜13年)の写真家、映画撮影技師だったことで知られている。
外国人として初めて日本陸軍に従軍し、日露戦争に参加して軍人を通して日本人を知り、その後3年間の日本滞在の体験から得た日本観、日本人観の基づく「この世の楽園 日本」(In Lotus-land Japan)を発行した。
原著は、全20章からなる大部であるが、訳本では10章に削られていた。
日本全国を旅行しての記録と写真が中心となっているが、「日本の婦人について」と「日本の家と子供」という章は、特別に設けられている。
ポンティングという人は、日本を何回も訪れて、何年か日本に住んだこともあり、日本人や日本文化についてもよく理解している。
日本全国を旅して、写真を撮って、その歴史も踏まえて書かれた文章は、外国の方が書いたとは思えないものである。
「日本の婦人について」という章は、次の文章で始まっている。
日本を旅行するときに一番すばらしいことだと思うのは、何かにつけて婦人たちの優しい手助けなしには一日たりとも過ごせないことである。
中国やインドを旅行すると、何ヶ月も婦人と言葉を交わす機会のないことがある。
それは、これらの国では召し使いが全部男で、女性が外国人の生活に関与することはまったくないからだ。
しかし日本ではそうではない。
これははるかに楽しいことである。日本では婦人たちが大きな力を持っていて、彼女たちの世界は広い分野に及んでいる。
家庭は婦人の領域であり、宿屋でも同様である。
優しい声をした可愛らしい女中たちが客の希望をすべて満たしてくれるので、宿屋についてから出発するまでの間に、いつの間にか貴方にとって彼女たちの存在がなくてはならないものに感じられるようになる。
私が読みたいと思っていた「日本の家と子供」という章は、訳本に納められていなかった。
ネットを検索していたら、archive.orgという図書館サイトに、原著があって読むことができることがわかった。
紙の書籍ではないのでスキャナーは使えない。考えた結果、iPadで表示したところを、スマホで撮影することにした。16ページほどなのでなんとかなりそうである。
英語なので、敷居は高いが、ゆっくり読んでいこうと思う。
こんな感じである。
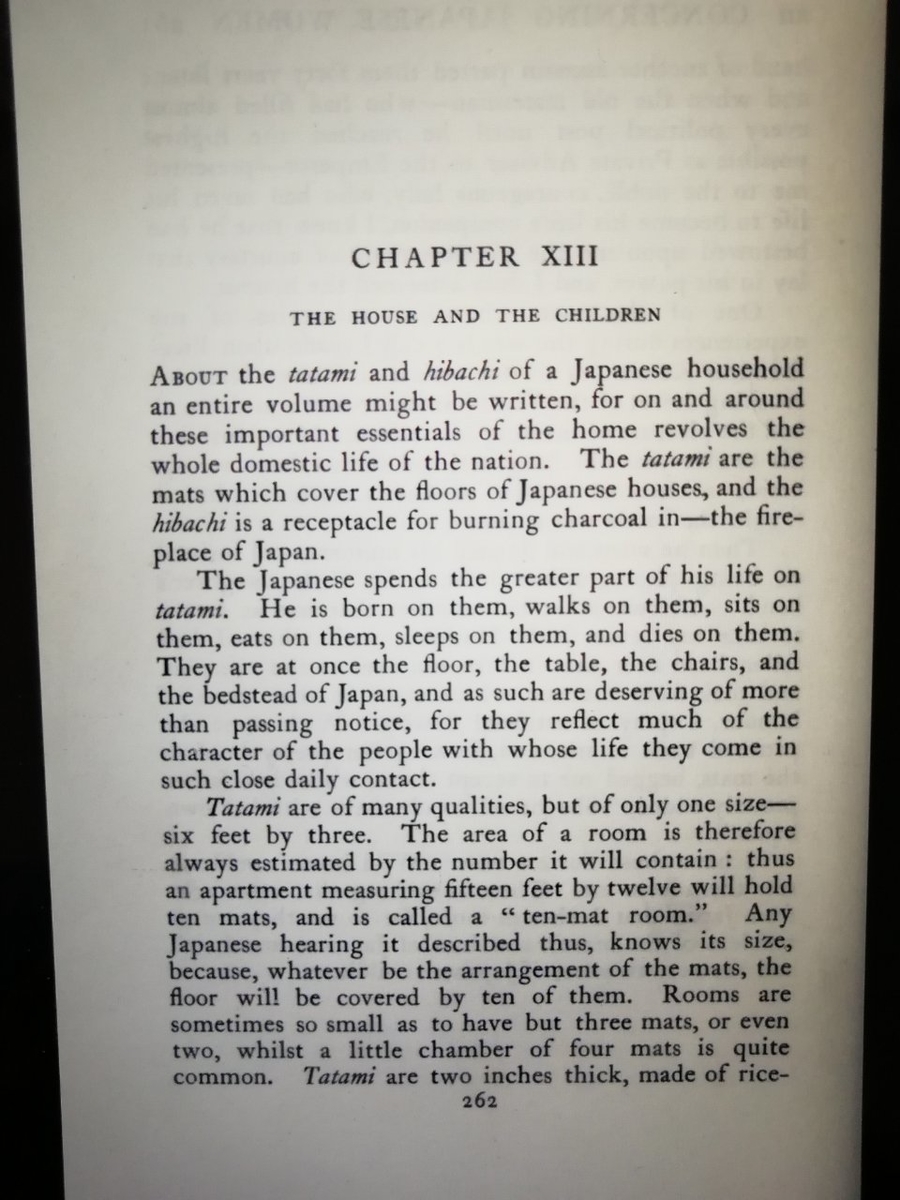
読み終わったら、内容について書いてみようと思う。